迷いの多いこの世において、私たちを導いてくれる「本」。近年、さまざまなかたちで取り入れられている読書療法(ビブリオセラピー)について、『ビッグイシュー・オーストラリア』が取材した。

Svetlana Larshina/iStockphoto
「読書療法(ビブリオセラピー)」とは、ギリシャ語で本を意味する「ビブリオ」と、癒しを意味する「セラペイア」に由来する。本を読むことの癒やし効果を指す幅広い用語だ。誰かに本を読んでもらう、セラピストによるグループ(または個人)セッションに参加する、読書会や文学講座に参加する等、さまざまな実践方法がある。
読書療法の立役者であるスーザン・マクレーン*1は、「文学作品の言葉を用いて、個人、家族、コミュニティ、社会全体に良い影響を与える行為」と表現する。読書療法のおかげで、人は心理的、社会的、感情的な問題と向き合いやすくなる、とマクレーンは言う。必ずしも本の中に答えを見つける必要はない。重要なのは、感情移入し、一つの問題をさまざまな視点で捉えられるようになることだ。「従来のセラピーとはまた違った可能性を提供できるので、人生のコマを進めるために助けを必要としている人のサポートになるのです」
*1 https://wordsthatheal.com.au
大の読書好きであれ、年に一冊しか読まない人であれ、物語はこの世界を渡り歩く私たちをナビゲートしてくれる。「ビブリオセラピストとしてのこれまでの経験から感じるのは、読むことを楽しむ楽しまないにかかわらず、そこに想像力が働いて、いろんな状況がありうると考えられることに、癒やしの効果があるのです」とマクレーン。
自身との対話を促す本を「処方」
では、読書療法はどんなふうに行うのか。そのプロセスは個々の読者によって異なるため、まずは読者の置かれた状況を知ることが先決、とマクレーンは話す。相談者が何を必要としているのか、どれくらいの読書習慣があるのか、どんな課題にぶつかっているのかなどを確認してから、マクレーンいわく「自身との対話を促す本」を処方する。
「洞察力を与えてくれ、異なる視点から物事をとらえられる可能性を秘めた本を選んでいます」とマクレーン。「読者を好奇心を引きつけ、深く考え、新しいアイデアを模索させられる本です。心をなだめ、これからの可能性に静かに思いをはせられる本です」
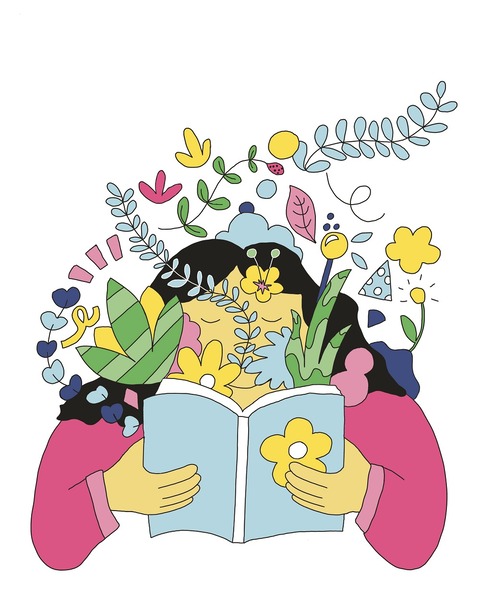
Illustration by Angharad Neal-Williams
パンデミックの影響で対面のセラピーが難しくなってからは、ポッドキャスト『ビクトリア州立図書館のビブリオセラピー』の発信も始めたマクレーン。「読書療法をデジタル版で提供することで、ウェルネスへの新たな取り組みになればと思ったんです。物語、詩、歌詞などを朗読し、リスナーがその作品のテーマや思考を掘り下げられる手助けになればと思っています」
現実逃避が必要とされる時代
自分と考え方が似ているなど、登場人物に自分を重ね合わせられる作品に惹かれたことはないだろうか。マクレーンは、摂食障害のある10代の女の子に漫画本を処方し、自分の気持ちと近い場面があれば、お父さんお母さんに読んで聞かせてあげてと提案した。すると、その子は3つの場面を選んで両親に読んで聞かせ、はじめて家族でいろいろ話せた夜になったという。
現実逃避させてくれる本に惹かれることもある。ビブリオセラピストで、『Reading the Seasons』(2021年3月刊行、未邦訳)の共著者ソニア・ツァカラキス*2は、パンデミックで不安も多いこの世の中で、本の世界は誰にとっても逃げ場になると語る。「終わりなきニュースとこの先に立ちはだかる不安にすっかり慣らされてしまっている私たちは、よい物語にひたる必要があります。現実から逃避させてくれるフィクションをかつてないほど必要としています。現実逃避はいいものです」
*2 http://www.literaryhand.com
支援の場で導入する動きも
本が持つ癒しの力を取り入れる組織も増えている。ビクトリア州最大規模のポート・フィリップ刑務所やホームレス支援施設「プラーグ・ハウス」で、読書療法を活用したプログラムを考案したマクレーンは、さまざまな人が一堂に会し、複雑なテーマを協力的かつ建設的に話し合うための実に有効な手段になると語る。
「物語の中の人物の声や考えを通すからか、より安心して話し合えるのです」。参加者たちの思いや感情、アイデアを具体化させるよう促しながら、話し合いを導いていく進行役には、読書療法のねらいをしっかり理解していることが求められる。
読書療法が大きな効果を持つ理由の一つは、多様なテーマを取り上げた本があるからだ。成功、失敗、もがき苦しんだ経験……本を読むことで、他の人がどんな生き方をしているのかを知る。よって、さまざまな本、本に関連したプログラムや支援サービスにアクセスしやすいことが重要となる。公共の図書館、そして司書の存在が欠かせない。本を読めるよう法整備されていること、そして学校で読書を奨励することも非常に重要だ。
日常生活に「読書療法」を取り入れてみてはいかがだろうか。誰だって孤独になりたくなんかない。本を読むことで、人との距離が少しだけ近くなるかもしない。
By Alicia Sometimes
Courtesy of The Big Issue Australia / International Network of Street Papers
ビッグイシュー・オンラインのサポーターになってくださいませんか?
ビッグイシューの活動の認知・理解を広めるためのWebメディア「ビッグイシュー・オンライン」。
提携している国際ストリートペーパー(INSP)や『The Conversation』の記事を翻訳してお伝えしています。より多くの記事を翻訳してお伝えしたく、月々500円からの「オンラインサポーター」を募集しています。
