編集部より:1月25日の「世界ハンセン病の日」に合わせて、日本財団が「THINK NOW ハンセン病」キャンペーンを実施しています。美術活動を通してハンセン病患者と向き合ってきた南嶌宏教授へのインタビュー記事です。
(日本財団ブログソーシャルイノベーション探訪より、一部編集して掲載)
人への優しさの根源を突き詰める ハンセン病 差別をなくすために

(ハンセン病元患者と向き合ってきた南嶌教授)
業病と呼ばれたハンセン病は効果的な治療法の確立で、世界的にも抑制され患者数も減少している。
その一方で患者、回復者に対する偏見・差別が抜きがたく残り、どう克服するのかが大きな課題となっている。差別はなぜ生じるのか、その解決策はあるのか。
ハンセン病と差別を世界に訴える「グローバルアピール」が日本で初めて発表されるのを前に、美術活動を通して日本や韓国、台湾などのハンセン病患者と向き合ってきた女子美術大の南嶌宏教授に社会的な課題について聞いてみた。(花田攻)
「太郎、啓発してきなさい」
その人形との出会いは、熊本市現代美術館のオープニングとして国際美術展の開催準備をしている2000年ごろだった。熊本県合志市にある国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園」で暮らしている遠藤邦江さんが、産むことを許されなかった自分の赤ちゃんの身代りに、買った抱き人形を「太郎」と名付け長年持っているということを知った。

(遠藤さんと一緒に生きてきた「太郎」)
「太郎」を見たときに愕然とした。自分が知らなければならない、多くの人に紹介しなければならないのは米国の現代美術など世界の最先端ではなく、自分の足元にあったということに。強烈なショックと恥かしさ、申し訳なさを感じた。
突き動かされるように遠藤さんを訪ね、「太郎」の美術館への貸し出しをお願いした。「一緒に生きてきたので見せるものではない」と、柔らかく断った遠藤さん。私たちが知らなければならない闇の中に隠された人間の真実、深い悲しみを背負っている人形だから是非にとお願いした。受け止めてくれた遠藤さんは太郎を抱きしめて、顔を見つめ「太郎、啓発してきなさい」と言って送り出した。
展覧会場のメインの場所。太郎はブランコに乗ったことはないだろうと、ブランコを作り乗せた。お母さんたちが見に来ると、説明がなくてもブランコに乗っている姿を見ただけで、目に涙を浮かべる。説明を見てうなずき、太郎の背中を押してくれる。母親の感性はすごいと思った。無関心で通り過ぎる人もいたが。
舌先で仏と出会う
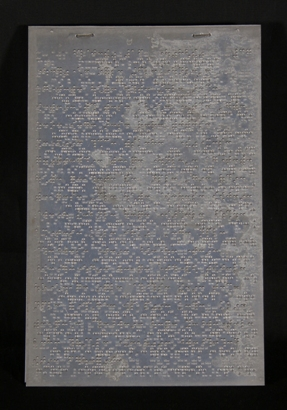
(経文が刻まれている「舌盤」)
2001年から全国にある13の療養所を訪ね歩いた。宮城県登米市の東北新生園で見せてもらった「舌盤」はショックだった。目が見えなくなると点字版を使うが、指先もないので舌で触れて金属板の文字を読む。そこまでして本を読みたいと。それは法華経の経文だった。舌先で仏と出会っていた。
「先生の立っている所に埋めたんです」

(上原さんの「いのちの貝殻」|南嶌教授提供)
海に囲まれた沖縄愛楽園(名護市)。元患者の上原ヨシ子さんが「先生の立っている所に埋めたんです」。明るく言う。妊娠した人が堕胎させられ、この海岸に埋めさせられた。そんな記憶を毎日引きずりながら、わが子と出会うかのように海岸の貝殻を持って帰っていた。沢山の箱いっぱいに集められた「いのちの貝殻」。子どもの代わりだったろう。この貝殻も貸していただき美術館に展示した。
人の優しさの根源はなんだろう
菊池恵楓園に通っていた2003年、県内の温泉旅館でハンセン病元患者の宿泊を拒否する事件が起きた。その時、園に届いた手紙・ハガキの8割が元患者を誹謗中傷する内容だった。日本は戦後、経済的に一流国になったかもしれないが、本当の意味での民意がこんなに低い国だということが、黒川事件でよく分かった。
美術に関わってきて思うのは、これは美しいと思う気持ちは自分の心のどこからくるのか、醜い、汚いと思うのはどこからくるのか。その延長上で、困っている人がいると「大丈夫ですか」と言う人間の優しさはどこからくるのか。毎日、親や教師から優しくしなさい、と言われていないのに弱い者に手を差し伸べるのは、どこからくるのか。
そういうことを日本では教えてこなかった、教育がなされてこなかった。小学生でもみんな優しさを持っている。それはどこから来るのかと問われれば考え込んでしまう。その考える時間が1分でも10分でもあれば。それを考えようねと、投げかけてくれる大人がいたかどうかが、その子の成長に決定的な種を植え付ける基になる。
みんな考えないわけではないが、発露していく空気がない。だから差別をし、差別を受ける。差別を撲滅するのは不可能だ。なくなってしまう瞬間に人間の存在は消える。それもあっての人間だからだ。
だけれども、人の優しさはなんだろうということを小さい時から、少しでも生活の中で持つこと、それを考えながら遠くを眺めている時間が与えられていたら、差別の感情は減少していく。
南嶌教授は元患者の皆さんを「お父さん」「お母さん」と呼ぶ
この人が自分の父親だったら、この人が自分の母親だったら差別するだろうか。絶対にしない。他人だと思うと放っとけと思ってしまう。差別を増長するベクトルが入る。自分の肉親だと思うと差別は出てこない。
学生にも話をする。ショックは受けるが歴史を学んでくる。そのことにより経験が一歩、身体化される。何年か前に学生と韓国・ソロクトにも行った。患者がいた部屋に寝泊まりし、食事のボランティアをした。自分の中の痛みであり、記憶ということを引き受けるきっかけを与える。
ハンセン病患者の人生に見る、希望と明るさ
極限の隔離された光の届かない場所でハンセン病元患者の人らは、どのようにして生きてきたのか。美術活動を通してハンセン病元患者と向き合ってきた女子美術大学の南嶌宏教授は「そこには希望や明るい人生をもった空間、時間があったからだ」と語る。
韓国・ソロクトの更生園。書道で文字を書いている人がいた。それはハングル文字で聖フランチェスコの祈りの言葉だった。差別されたものが差別したものを許す、という言葉。その言葉を毎日、念じながらすべてを許してきた。ハンセン病かどうか関わらず人間にとってとても大切な言葉の1つ。その作品も熊本現代美術館に借りてきた。
人のために生きる
ここで盲目のピアニスト、金新芽さんに出会った。
もう亡くなったが、日本にも何回か招待されて来ている。旧制高校を出たころから目が見えなくなり、ハンセン病に。絶望はするが、コロニーをつくり、子どもたちに「勇気を失ってはいけない。君たちだって世の中でいろんなことができる」と、楽団を結成し、刑務所の塀の外から慰問する活動を続けた。
こんなすごい人たちがいたんだ。絶望して自殺した人も多いが、その中でも希望を持って、なおかつ誰か人のために生きてきた人がこんなにいるのか、と思った。
台湾・楽生院。100円ショップで売っているようなスケッチブックに、女の人の絵を上手くはないが一所懸命に描いている。
「お父さんこれはどうやって描いたの」と聞くと「本当は女の人の裸を描いたの。それだけだとだけど恥ずかしいから、後で服を着せているの」。汚れのない人間てそういうものだな、ということを感じさせてくれる。
絵自体は下手だが、神様はこういうために人間に絵を与えてくれたんだと教えてくれたのが、世界的に有名な芸術家ではなく、国内外の療養所のお父さんであったり写真であったり、書であったりする。
すがすがしい人生
日本の療養所を回っても、看護師と元患者の恋愛、結婚の話など本当に生々しい人間の姿を、お父さんたちが教えてくれた。もちろんひどい仕打ちも受けていた。小学生の時、先生が試験の解答用紙を渡すとき、ビニール手袋をして渡す。成績表も手袋をして渡される。その時の子どもたちがどんな思いだったろうか。
極限の生活についてオーラル・ヒストリーとしてこれまで明らかにされている。しかし、その中で、抜け落ちているのは、たしかに絶望に追い込まれる生活だったかもしれないが、こんなに深い希望に生きてきた人でもあったという記録だ。彼らを極限の隔離される場所にあって、光の届かないあの場所にあって、でもなおかつ生きるぞ、と思わせる希望とはなんであったか、ということを採集しようと思っている。
彼らがどんな明るい人生を持っていたか。そんな空間、時間があったのかと誰もが思う。だが、これがなかったら人間は生きられない。元患者の話を聞いているだけでも、真っ青な空に白い雲がたなびいている、というくらいのすがすがしい人生をそれぞれが持っている。
人を根源的にとらえる
野球に明け暮れた青春、村芝居みたいな歌舞伎。「婦人部なんですよ」という人。それはなんですかと聞くと、「女の人の尻を追いかける」。恋愛の話は本当に面白い。だけど、どこか悲しい。こんなことを残さないで何を残すのか。隔離された人間となにか、こういう人たちだという記録になるのではなく、もっと根源的な人間とはなにか、人間とはこういう存在だということを指し示す記録としたい。
本当に明るい、ハンセン病療養所の中のきらめくように明るい記録。腹をかかえて笑いたくなるようなハンセン病に関する本にまとめたい。そうでもなかったら彼らの人生は浮かばれない。暗くて、辛くて、それはそうだったしきちんと残すとしても、それだけではないはずで、私たちだって辛いことだらけだけど、ちょっとの1割ぐらいの喜びがあるから、何とか生きてこられた。その根源的なモデルが彼らなのだ。
ハンセン病を語る語り口を画一化しない。こんなに面白いから療養所に行こうよ、というムーブメントは作れる。元患者から「よく来てくれたね。こんなことを伝えたかったんだ」と話をしてもらう。若い人に、一度小さな経験をさせたら、どんどん広がりを持つ。
こういうことを聞いたらいけないのかと思いこんで、最初から縮こまらずに、何でも受け止められるだけの経験をしてきた人たちが、君たちを迎えてくれるんだよ。むしろ人生相談に行けよと、勧めたい。
(花田攻)
写真提供:南嶌宏教授
みなみしま・ひろし
1957年長野県生まれ。筑波大学卒。パリのカルティエ現代美術財団、熊本市現代美術館館長などを経て、女子美術大学芸術学部芸術学科教授。武蔵野美術大学客員教授。美術評論家。ヒロシマ、アウシュビッツ、ハンセン病、東日本大震災などの経験を「世界回復」への導きの経験として受け止め、芸術表現の意味を根本的にとらえ直し続ける。著書に「豚と福音」など。
