『フレンズ』のチャンドラー・ビング役で知られる俳優マシュー・ペリーは、2022年に発表した自伝『Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir』の中で、鎮痛剤オピオイドの服用が元で腸が破裂したと述べている。人工肛門袋(ストーマ袋)を使う生活となった後、翌年54歳で死去。
処方薬であるオピオイド(コデインやヒドロコドンなど)の服用で、本当に腸が破裂する事態が起こり得るのだろうか?ーー英バンガー大学社会精神医学教授ロブ・プールが『The Conversation』に寄稿した記事を紹介する。
オピオイドが腸や呼吸にもたらす影響
オピオイドは腸の活動を抑える作用があることから、下痢の症状緩和に用いられることもあり、便秘になりやすい。服用を続ける中でいろんな作用への耐性ができていくが、便秘に関しては改善が見られにくく、悪化することも。ひどい場合、腸が伸びて、元に戻らないこともある。腸に既往症があれば悪化する恐れもある。とはいえ、ペリーのように腸に穴が開くケースは非常に稀だ。
オピオイドの成分であるアヘンケシに鎮痛作用があることは、数千年前から知られていた。しかし、予期せぬ作用もある。薬理学的に最も恐ろしいのは呼吸を抑制する作用だ。脳幹にある呼吸中枢を低下させるため、多量に服用すると呼吸が止まる恐れがあるのだ。耐性ができることで鎮静作用は緩和される一方、呼吸への影響はそれほど弱まらない。服用量が増えると、血中酸素レベルが下がる。オピオイド過剰摂取が死因とされているミュージシャンのトム・ペティやプリンスも、この呼吸抑制作用が働いたと考えられる。

長期服用により鎮痛作用は低下するため、かえって服用量が増えることも多い。妙な話だが、経口モルヒネの服用量1日あたり120ミリグラムを超えると、かえって痛みが悪化する。これは「オピオイド誘発性痛覚過敏」と呼ばれ、その原因は分かっていない。
アルコールと違い、オピオイドは臓器そのものへの直接的ダメージはないが、男性のテストステロンの低下(性腺機能低下症)を引き起こし(女性ではそれほど一般的ではない)、どの程度回復させられるかはまだ分かっていない。
認知や行動への影響
オピオイドの服用量が増えると、認知や行動に一時的に変化が起きる。鎮静効果により注意力や集中力が低下し、抽象的思考や多角的理解にも影響が出る。喜びを味わう力も低下し、さまざまな活動への関心も失われる。交友関係や家族生活がどんどん狭まり、断絶することも。だが、こうした行動変化は基礎疾患や痛みによるものとされ、実はオピオイドの抑制効果によるものだということは十分に理解されていない。
急激に増えやすい服用量
それでも望みがないわけではない。長期的にオピオイドを服用している場合でも対策はある。オピオイドは高用量より低用量の方が鎮痛効果が優れ、中には鎮痛剤を止めてしまった方が痛みがおさまる場合もあるのだ。指導の下に、副用量を少しずつ減らしていくことをおすすめする。しかし、ひとたび高用量の服用に至ってしまうと、そこから抜け出すのは極めて難しくなるので注意が必要だ。
これまで、オピオイドの服用量は少しずつ増えるもので、服用量に問題があると判明する頃には手遅れになっていると考えられていた。ところが、筆者のチームがウェールズの一次医療におけるオピオイドの高用量服用者の記録を分析したところ*1、服用量が少量ずつ長期的に増加した事例は一切なく、すべての事例において、数週間、人によっては数日の短期間のうちに、経口モルヒネの服用量1日あたり120ミリグラムと同じかそれ以上に匹敵する服用量に達していた。服用開始からすぐにそうなった場合もあれば、何年間も低用量で服用した後に、突如として服用量が急増した場合もあった。また、高用量のしきい値を一度超えた後で、低用量に戻る事例はなかった。
*1 Patterns of prescribing in primary care leading to high-dose opioid regimens: a mixed-method study
筆者が関わった以前の研究*2 では、高用量のオピオイドを服用していた者に、メサドン(別のオピオイド)の低用量服用に切り替えさせる処置を施した。メサドンは体内で分解されるのに時間がかかり、血中濃度が一定に保たれるので、服用量を低く抑えるのに適しているのだ。結果、20人の被験者が、活動レベルや幸福度が大幅に改善したと報告した。痛みが軽減した、あるいは痛みに対処しやすくなった、と報告する者もいた。希望者には元の投薬計画に戻る選択肢が与えられたが、誰もそれを選ばなかった。

私は、オピオイドの服用を一切やめろと言うつもりはない。だが、低用量の服用で鎮痛効果が見られない場合は、服用量を増やしたところで痛みを管理できるようになる可能性は低いことは周知されるべきだろう。
By Rob Poole
Courtesy of The Conversation / International Network of Street Papers
※2025年10月1日発売の『ビッグイシュー日本版』512号の特集は「人間と薬物。そのつきあい方」。薬物の歴史や、日本における「見えない危機」について特集している。
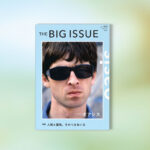
あわせて読みたい
サムネイル:Rattankun Thongbun/iStockphoto
ビッグイシュー・オンラインのサポーターになってくださいませんか?
ビッグイシューの活動の認知・理解を広めるためのWebメディア「ビッグイシュー・オンライン」。
提携している国際ストリートペーパー(INSP)や『The Conversation』の記事を翻訳してお伝えしています。より多くの記事を翻訳してお伝えしたく、月々500円からの「オンラインサポーター」を募集しています。

