(その4を読む)
ここからは総括的なものを書く。最初に注意事項として書いたとおり僕の人生における登場人物の中に悪人はひとりもいない。つまりは奇跡的な確率で僕は運が悪かった、ということだ。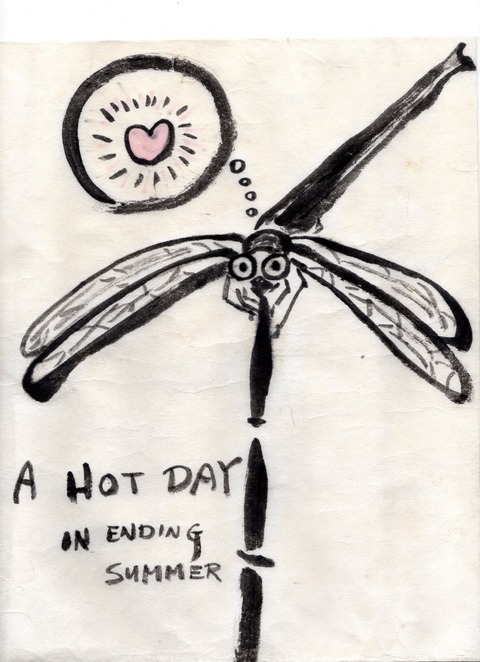
兄は本当に優しい人だった。今は10年会っていないし、会いに行けば兄を追い詰めると思っているから会いにも行けない。そんな関係だけれど母から伝え聞くところによると、いつも兄は「○○○○(僕の本名)のことを気にかけてやってくれ」と、毎回言うらしい。本音だと思う。ただ、優しすぎたがゆえに色々なモノに傷付けられすぎた。
兄は僕に殴られる痛みを教えてくれた。そして同時に殴る痛みを感じていた。僕も殴り返すべきだった。兄を殴って殴る痛みを知ればよかった。兄に殴られる痛みを感じてもらえば良かった。そうしたら僕らは対等でいられた。僕らは対等ではなかった。同じ痛みを共有すれば良かった。
母とは必死さ、一所懸命さを競った。それが正しかったか正しくなかったのかなんてどうでもいい。僕は母に僕の凄みを見せつけた。母は僕に母の凄みを見せつけた。それだけで良かった。ごちゃごちゃ考える必要もない。他の人に理解してもらう必要もない。父も兄も僕も母も生きている。それ以上もそれ以下も無い。それだけで十分だ。大満足だ。
父には人間臭さを学んだ。色々と父には苦労をさせられたが、今思い返してみれば父の行動には筋が通っている。ハッキリ言って父親としては正しくは無かった。ただ、正しくはないが生き方としては筋が通っていた。だから今では父の思い出はエンターテイメントとして僕の中では昇華されている。事実は小説よりも奇なりとはよく言ったもので、世に発表出来ないような話も含め、父の人生はネタだらけの人生だ。
それに全力で逃げることも教わった。それは周りの人に迷惑をかける最低な行為ではあるが、最低限命は守れることは教わった。それと同時に親の死に目に会えないことも学んだ。人として間違ったことをしすぎると親の死に目にはあえないのだ。これほど不幸なことはない。
ちょっとだけ父の話を続ける。僕が二十歳の頃に父は自己破産をして行方知れずになった。何年も音信不通だったが、どこからどうやって番号を入手したのかは知らないが僕の携帯に電話をかけてきた。それから1年に一度ほど電話をかけてくるようになった。ほどなくして父方の祖父が亡くなった。僕と母、縁は切れたにも関わらず叔母さんに亡くなる直前の病院と葬式に呼んでもらえた。 父は呼ばれなかった。当たり前の話だ。その後はたまに叔母さんと祖母に会いに昔の家を訪ねることが増えた。父はたくさんたくさん親戚に迷惑をかけた。特に叔母さん夫婦や祖父母に迷惑をかけた。それでも親子の絆っていうものは変わらないのだろう。叔母がいる前では絶対に口にしなかったが、僕と祖母が二人きりになると祖母から「父はどうしているか?」と毎回尋ねられた。僕は「うん、なんとか元気にはしてるみたいだよ」と言うのが精一杯だった。
たまたまの話だけど、その頃から僕は年に一ヶ月ほど農作業のバイトをするようになった。少しずつだけど貯金もした。その頃、僕に目標みたいなものがひとつできた。父の借金については大人たちの話し合いで処理されていたから僕は細かな詳細は知らなかった。だけど一晩で300万円借金してきたときに「こんな人でも兄だからね」と、肩代わりしてくれたのは叔母さん夫婦だったことだけは知っていた。叔母さんは長男である父に代わって祖父母の面倒を見ていてくれた。だから僕は300万円貯まったら叔母夫婦に300万円お返しして、土下座でもなんでもして父と祖母を会わせたいと考えるようになった。
けれど、年に一ヶ月ほどの短期のバイトで300万円貯めるなんていうことは夢のまた夢のような話だった。そして僕が30歳のときに祖母が亡くなった。凄く落ち込みもしたけれど、叔母は葬式に僕と母を呼んでくれた。祖母とのお別れも出来た。親戚から祖母の思い出話も聞くことが出来た。祖母の若いころの写真はびっくりするくらい美人だった。そんなこんなをしながらも、父の事が頭からずっと離れなかった。叔母に言えば父と祖母が最期の別れをすることくらいは許してくれたかもしれない。でも父のしてきたことを考えれば筋が通らなすぎて言えなかった。
祖母が焼かれるときには、父は祖母が焼かれて骨になることすら知らないんだなと思ってなんとも言えない気持ちになった。全てが終わってから父に連絡を取ろうかとも思ったが連絡はしなかった。叔母が連絡をしていないのであれば僕が連絡を取ることは筋の通らないただのワガママでしかないと思ったから。
それからモヤモヤした気持ちを抱えながら生活をすることになった。精神的にも肉体的にも少しずつ削られていった僕は、三ヶ月後にかかってきた父からの電話で感情を抑えることが出来なくなって父に祖母の死を伝えた。父は静かに「そうか・・・そうか・・・」と何度かつぶやいたあとにせきを切ったかのように号泣しながら「すまんかった・・・すまんかった」と繰り返し謝った。誰に対して謝っていたのか分からないが、それを聞きながら僕も号泣した。自業自得なのだ。そんなことは重々承知していた。だけど涙が止まらなかった。親の死に目に会えないということがどれほど親不孝なことかと父を通して学んだ。
今回色々と家族について書いてみてハッキリとしたことがある。やはり僕は家族のことが好きなのだ。
父も母も兄のことも僕は大好きなんだろう。だから恨めなかったし憎むことも出来なかった。おかげで凄く遠回りをさせられたし、苦労もした。だけど結局僕は家族が好きなのだ。父にしても兄にしても母にしても何一つ完璧じゃなく、凄く人間臭い人たちだった。そんな家族だったから僕は特等席でエンターテイメントを味わえたのだと思う。
父がゴクゴク飲むキャラクターがプリントされたボトルの空き瓶に農薬を入れて死のうとした件にしたって今から振り返れば壮大なコントだったようにも思う。もちろん演者である僕や母は大変な思いをした。だけど大変な思いをしたからこそ僕だけのオリジナル体験が出来あがったのだ。
体験しようと思って出来るものじゃない。(体験したい人もいないだろうが)狙って出来ることじゃない。ひたすらにいびつで完璧じゃない家族が人間臭く必死に生きた。生き抜いた。だからこそ僕の人生は一大エンターテイメントになったのだ。
僕の過去の人生は無駄だったという視点を捨てたわけではない。何かを悟ったわけでもない。でも、僕はつきゆび倶楽部という凄く遠回りな表現方法で、家族のことがやっぱり好きなんだと気付かされた。
僕の中には数え切れないほどの視点が存在している。どれもこれも本当の自分だ。嘘の自分なんてひとりとしていやしない。視点がめまぐるしく頭の中で変わりながら文章を書いているため、読んでくれている人には伝わらないかもしれない。でも、今現在の視点でちゃんと書いておきたい。僕の人生は素晴らしいエンターテイメントだった。父と母と兄の家族に迎えてもらって本当に良かった。僕は不幸なんかじゃなかった。生まれてきたことは間違いじゃなかった。生きていて本当に良かった。ありがたい、ありがたい、ありがたい。ただただひたすらにありがたい。ありがたい。
下田つきゆび(つきゆび倶楽部)
1983年高知県生まれ。中2から3年間の完全ひきこもりを経て、定時制高校、短大に進学。
30歳を機に地域のひきこもり支援機関や病院に行くようになり、強迫性障害とADHDと診断される。
31歳でひきこもり経験を活かした「つきゆび倶楽部」という表現活動を始める。
現在はひきこもりがちな生活を送りながらもWRAP(元気回復行動プラン)のファシリテーターとして活動中。
