
-
 イベントレポート
イベントレポート
お金に不自由のない家庭環境に育った男性が、路上へ出てしまった理由とは——ビッグイシュー販売者が大阪府立吹田高校へ出張講義
有限会社ビッグイシュー日本では、ビッグイシューの活動やホームレス問題への理解を深めるため、高校や大学で出張講義をさせていただくことがあります。 今回ビッグイシュー日本の大阪事務所長・吉田と販売者の入島さんが向かったのは、 […] -
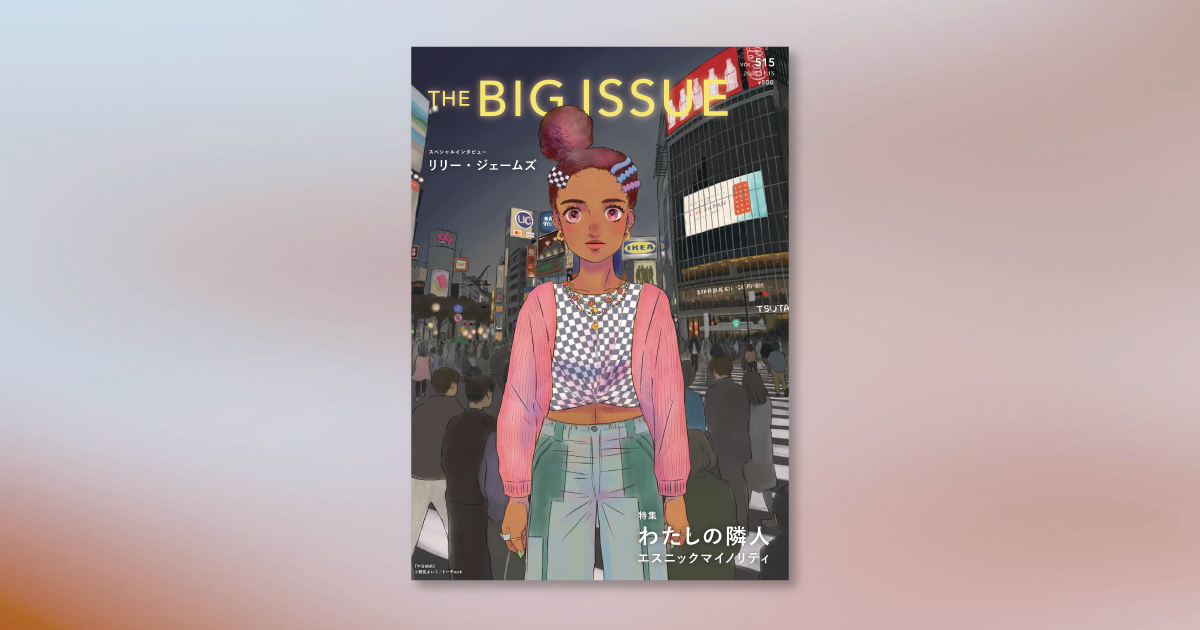 ビッグイシューのご案内
ビッグイシューのご案内
表紙&特集は「わたしの隣人 エスニックマイノリティ」、スペシャルは「リリー・ジェームズ」/11月15日発売の『ビッグイシュー日本版』515号
リレーインタビュー 私の分岐点)俳優 弓削智久さん 1999年に「小市民ケーン」で俳優デビューし、2002年には「仮面ライダー龍騎」(テレビ朝日系)の由良五郎役で注目を集め、映画やドラマを中心に活躍を続けている弓削智久( […] -
 公正・包摂
公正・包摂
「ベーシック相続」で格差社会の是正を目指すー2家族が国民半分の合計資産より多くを占有するドイツの現状
日本だけでなく世界中で広がる格差問題。その理由と対策について、政治学者マルティナ・リナルタスにドイツ・ハンブルクのストリートペーパー『ヒンツ&クンスト』誌が話を聞いた。 『ヒンツ&クンスト』誌:あなたは「ドイツは実力主義 […] -
 原発ウォッチ!
原発ウォッチ!
世界銀行とアジア開発銀行が原発融資解禁へ/原発推進国が強く働きかけ
国際開発金融機関(MDB:Multilateral Development Bank)は途上国の貧困削減や持続的な経済・社会的発展を金融や技術などで支援することを目的に、各国の出資で設立された金融機関だ。世界銀行(以下、 […] -
 平和・協同
平和・協同
戦争がもたらす環境破壊を記録する動き
戦争は、軍人・民間人問わず甚大な犠牲者を出す。何百万人もの人が、遺族の悲しみ、負傷者の不安、家を失う不安を抱えることになる。人間が負う苦しみの前では、戦争が気候や環境にもたらす影響は見過ごされやすい。だが実際のところ、武 […] -
 健康・衛生
健康・衛生
毎年10万人以上を殺し、依存症者を生み出し続ける鎮痛薬「フェンタニル」
米国アラバマ州モービル郊外ーーコリー・ジェイムズ(40歳)が友人を亡くした夜のことを語る。「救急車を呼んだけど、手遅れだった。あんな状況を目の当たりにして、これは本当にヤバいって思ったんだ」。手術後の痛みを和らげるために […] -
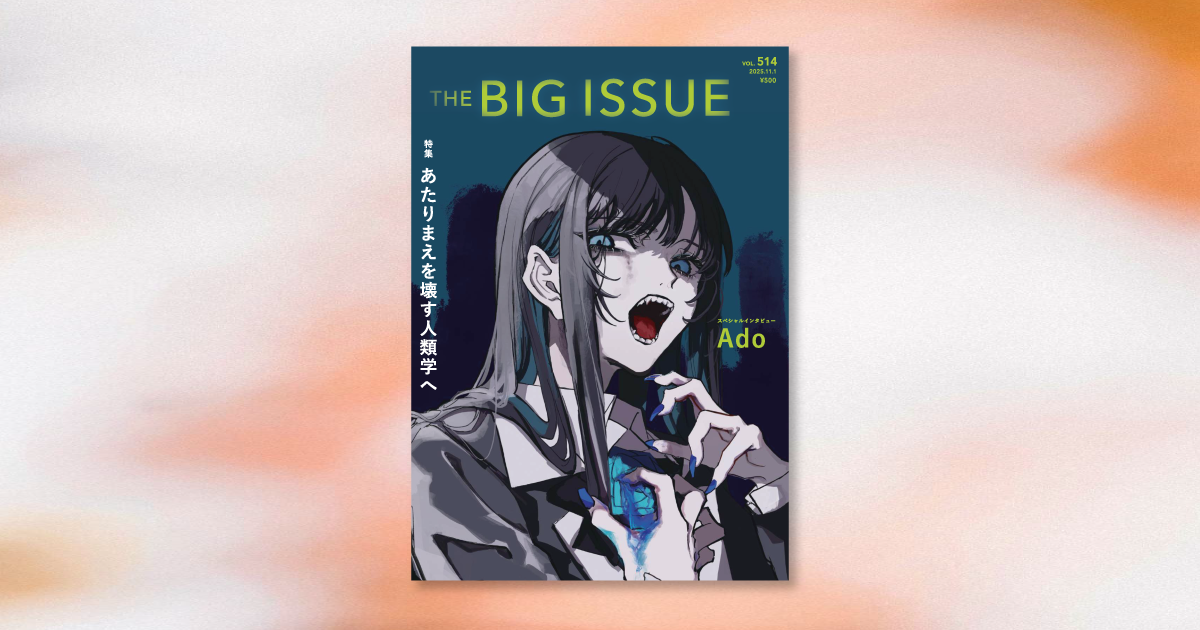 アート・文化
アート・文化
表紙は「Ado」、特集は「あたりまえを壊す人類学へ」/11月1日発売の『ビッグイシュー日本版』514号
11月1日発売の『ビッグイシュー日本版』514号の表紙は「Ado」、特集は「あたりまえを壊す人類学へ」です。 (リレーインタビュー 私の分岐点)俳優 金城大和さん 2010年に俳優としてデビューして以来、舞台や映画、テレ […] -
 平和・協同
平和・協同
もし吉祥寺がガザだったら――高橋真樹さんによる『ガザ・サーフ・クラブ』解説
ガザについて報道されるとき、映し出されるのはたいてい、爆撃シーンや瓦礫に覆われたまちの光景ではないだろうか。それは、「視聴率が取れるから」と「わかりやすい」映像や写真が使われるからだ。爆撃の前に何が起こっているかは、ほと […] -
 公正・包摂
公正・包摂
ガザの現実を「憎しみの連鎖」で片づけない――高橋真樹さんが語る『私は憎まない』の背景
日本では、大手メディアによるガザの報道は減ってきている。そして報道される場合でも、「憎しみの連鎖」や「宗教の問題」などという誤解を生む表現が使われるケースもある。しかしこの報道の裏には、長年続いてきた封鎖と占領、そして見 […] -
 平和・協同
平和・協同
空爆の合間の “ふつうの暮らし”――映画『ガザ 素顔の日常』上映と関根健次さんトーク
2025年10月、吉祥寺で、大手メディアがあまり報道しないテーマにスポットライトを当てた「UNKNOWN cinema」開催された。第1回となる今回はパレスチナのガザ地区を舞台にした4つのドキュメンタリー映画が上映され、 […]
タグから探す
- DIY
- DV
- LGBTQ
- PFAS
- Web3
- アスペルガー症候群
- アニマルウェルフェア
- アフガニスタン
- アフリカゾウ
- アメリカ
- アルゼンチン
- イギリス
- イスラエル
- イタリア
- インターン
- インド
- うつ病
- エスワティニ
- エネルギー
- オーストラリア
- オーストリア
- オランダ
- カナダ
- ギャンブル
- ギリシャ
- ケニア
- サステナビリティ
- シエラレオネ
- シリア
- スイス
- スウェーデン
- スコットランド
- ストレス
- スペイン
- スポーツ
- セルビア
- ソーシャルアクション
- ダウン症
- ダンス
- チリ
- デンマーク
- ドイツ
- トランスジェンダー
- トランプ
- ニュージーランド
- ハームリダクション
- ハウジングファースト
- パナソニックNPO/NGOサポートファンド
- パレスチナ
- ハンガリー
- ひきこもり
- ビッグイシューにかかわる人たち
- ひとり親
- フードロス
- ファイザープログラム
- ファッション
- フィリピン
- フィンランド
- フェアトレード
- フェミニズム
- ブラジル
- プラスチック
- フランス
- プロボノ
- ベーシックインカム
- ポートランド
- ホームレス・ワールドカップ
- ホームレス人生相談
- ホームレス問題
- ボディイメージ
- ボブ猫
- ポルトガル
- マイクロファイナンス
- メキシコ
- ロシア
- ロマ
- 三重県
- 不登校
- 中国
- 中央ろうきん
- 京都府
- 人種差別
- 依存症
- 兵庫県
- 再生可能エネルギー
- 写真
- 北朝鮮
- 北海道
- 千葉県
- 南アフリカ共和国
- 台湾
- 和歌山県
- 図書館
- 坂本龍一
- 埼玉県
- 大阪府
- 奈良県
- 奈良美智
- 女性ホームレス
- 子どもの権利
- 宇宙
- 宮城県
- 宮崎県
- 山口県
- 山形県
- 山梨県
- 岐阜県
- 岡山県
- 岩手県
- 島根県
- 幸福度
- 広島県
- 当事者の声
- 徳島県
- 恐竜
- 愛知県
- 感情
- 新型コロナウイルス感染症
- 新潟県
- 映画
- 東京都
- 枝元なほみ
- 栃木県
- 格差社会
- 歴史
- 死刑
- 民主主義
- 水資源
- 水道
- 沖縄県
- 滋賀県
- 滝田明日香
- 演劇
- 熊本県
- 生活保護
- 生物多様性
- 生理の貧困
- 石川県
- 神奈川県
- 福井県
- 福岡県
- 福島県
- 秋田県
- 科学
- 移民・難民
- 統合失調症
- 絵本
- 群馬県
- 肉食
- 自殺
- 自閉症
- 若者の活躍
- 茨城県
- 葬儀
- 言語
- 認知症
- 資本主義
- 選挙
- 銃
- 長崎県
- 長野県
- 青森県
- 静岡県
- 韓国
- 音楽教育
- 高知県
- 高齢者
- 鳥取県
- 鹿児島県
